10月度その24 世界の北方磁場強度シリーズ➡サンファンの地磁気変動3年間を調べ、GOES-16Eと準リアルタイム波形3日間を比較する!
世界の北方磁場強度シリーズ➡サンファンの地磁気変動3年間を調べ、GOES-16Eと準リアルタイム波形3日間を比較する!
以前、サンファンの北方地磁気変動3年間を追ったのですが、データが飛んでいて止めた経緯があります
しかしサンファン北緯18.1度西経66度の西経66度は、ブラジル磁気異常地点南緯30度西経60度に西経で近く、ここはあきらめきれずに有効なデータのみでグラフを出してみました

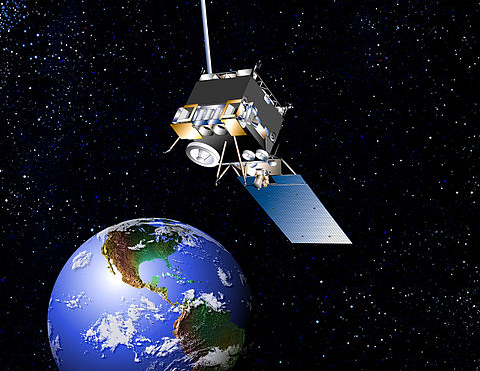
です
お付き合い頂ければ幸いです
まず、地磁気一般と当ブログモデルと電離圏一般です
地表の磁場強度マップ2020年は:
ESAより地球全体を示せば、

当ブログの磁極逆転モデルは:
1.地球は磁気双極子(棒磁石)による巨大な1ビット・メモリーである、地球内核は単結晶の固体鉄であって永久磁石として磁場方向を記憶している
2.この1ビット・メモリーは書き換え可能、外核液体鉄は鉄イオンと電子の乱流プラズマ状態であり、磁力線の凍結が生じ、磁気リコネクションを起こし、磁力線が成長し極性が逆で偶然に充分なエネルギーに達した時に書き換わる
[世界初!地球中心部の超高圧高温状態を実現 ~ようやく手が届いた地球コア~ — SPring-8 Web Site] さんの図に説明追加させて頂ければ:

3.従って地球磁極の逆転は偶然の作用であり予測不可でカオスである
地磁気方向定義とは:

電離圏とfoF2とは [電離層(Ionosphere)について解説] さんより:

上図は昼の状態で夜から昼への移行モデルを示せば [Ionosphere - Wikipedia] より、By Carlos Molina

電離圏S4シンチレーションマップはオーストラリア政府 [SWS - Section Information - About Ionospheric Scintillation] より

[バンアレン帯 | 天文学辞典] によれば、

南緯30度西経60度を中心とするブラジル磁気異常では、地磁気が弱く内帯の端は高度200km程度まで降下しています
ここから本文です
1.まずサンファンSJG3年間の北方地磁気変動と最大値最小値カウントグラフです

何と増加でした!
2019年10月から2020年9月までが飛んでいますし、2021年初めも飛んでいますが、増加であることは間違いのない所でしょう(平均値は、このグラフに現れた点のみの平均を取っています)
ここで、このグラフに現れたデータのみを使って24時間の最小値・最大値出現時刻と回数をプロットすると、

となり、カウント総数は3年間1095日の約2/3となっています
最大値と最小値のカウント数は同じ程度ですが、少し最大値ピークの方が高い傾向を示しています
最大値ピーク観測時刻UT15時台は、SJGでLT10.5時台となります
2.そこでSJG磁力線を求め、GOES-16Eとの準リアルタイム波形3日間グラフを取ります

SJG磁力線の高度は260kmと低く、GOES-16E高度35,786kmは出していません
260kmというと通常ですと電離圏F2層をかすめる高さ(昼間)です、北緯18.1度なので共役点は南緯18.1度であるとすればブラジル磁気異常の南緯30度には届いていません
波形グラフ3日間は、

最大値に関して同相な波形を示しています、OTTが逆相となったのに対し正反対の波形(最大値に関して、です)となりました
16EとSJGの時差は約0.5時間です
まとめ:
1.サンファンはデータが飛ぶので統計上信頼性に欠けるかな?とは思ったのですが、3日間の波形であれば問題ないだろう(データが飛んでいなければ)と思ってプロットしてみた次第です
2.結果は16Eと最大値に関して同相となりました
SJG西経66度と16E西経75度は約0.5時間の時差と近く、波形の比較が容易です(目視で、の意味です)
私の推論では、SJG磁力線ルートは電離圏プラズマとの相互作用は少なくかつバンアレン帯の影響はないだろう、ということになります(OTTと比べて、ですが)
以上、お付き合い頂き、誠にありがとう御座いました
感謝です